だが、それはそれとして、先ほど行程を整理する途中で、印象的な場面を二箇所、レジュメに引用しておきました。この紀行文の基本性格にかかわる一面が露呈していると思われたからです。
その一つは、竜飛の宿に泊まった翌朝、語り手の「太宰」が童女の可憐な手毬歌を聞いて、その「美しい発音」に心打たれる場面です。
《引用》
翌る朝、私は寝床の中で、童女のいい歌声を聞いた。翌る日は風もをさまり、部屋には朝日がさし込んでゐて、童女が表の路で手毬歌を歌つてゐるのである。私は、頭をもたげて、耳をすました。
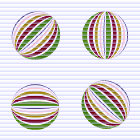
せッせッせ
夏もちかづく
八十八夜
野にも山にも
新緑の
風に藤波
さわぐ時
私は、たまらない気持になつた。いまでも中央の人たちに蝦夷の地と思ひ込まれて軽蔑されてゐる本州北端で、このやうな美しい発音の爽やかな歌を聞かうとは思はなかつた。かの佐藤(弘)理学士の言説の如く、「人もし現代の奥州に就いて語らんと欲すれば、まづ文芸復興直前のイタリヤに於いて見受けられたあの鬱勃たる台頭力を、この奥州の地に認めなければならぬ。文化に於いて、はたまた産業に於いて然り、かしこくも明治大帝の教育に関する大御心はまことに神速に奥州の津々浦々にまで浸透し、奥州人特有の聞きぐるしき鼻音の減退と標準語の進出とを促し、嘗ての原始的状態に沈淪した蒙昧な蛮族の居住地に教化の御光を与へ、而して、いまや見よ云々。」といふやうな、希望に満ちた曙光に似たものを、その可憐な童女の歌声に感じて、私はたまらない気持であつた。
(「四 外ヶ浜」 太字は亀井)
語り手の心が無心な童女の歌声によって浄化されてゆく。その感動がそのまま伝わってくるような、美しい表現です。ですから、細かいことにこだわる無粋なことはしたくないのですが、しかしこれは毬をついて遊ぶ時に歌う、あの手毬歌なのでしょうか。
女の子が向き合って「せっせっせ ぱらりとせっ/夏もちかづく 八十八夜」と、小学唱歌の「茶摘(ちゃつみ)」を歌いながら掌を打つ。あの遊びは、もちろん私も知っています。しかし、この歌に合わせて手毬をつくことはなかったのじゃないか。それに、この童女は「野にも山にも/新緑の」と歌ってゆくわけですが、これは「茶摘」の「野にも山にも/若葉が茂る」と、「花ごよみ」という唱歌の「野べも山辺も新緑の/風に藤波さわぐ時」を重ねた、いわば掛詞の形になっている。そういう語呂合わせみたいな歌い方が、子供たちの間に流行っていたかどうか。これも疑わしい。
それだけでなく、このささやかなエピソードを取り上げて、語り手の「太宰」は、「かしこくも明治大帝の教育に関する大御心はまことに神速に奥州の津々浦々にまで浸透し、奥州人特有の聞きぐるしき鼻音の減退と標準語の進出とを促し」云々と、佐藤(弘)理学士の言葉を借りて、意味づけをしていました。ずいぶん大袈裟な意味づけだ。そういう印象は否定できないところでしょう。
それやこれやを考え合わせますと、竜飛の宿で太宰が女の子の歌を聞いたことは間違いないとしても、東京でその経験を原稿化する時、かなりデフォルメを施していたのではないか。そんなふうに思われてなりません。
「花ごよみ」という唱歌は、「秋の花草多けれど 中にも君の千代八千代/祝うや 菊の花の宴」と、長寿を言祝(ことほ)ぐ言葉で結ばれていました。「菊の花」は皇室の紋章を暗示し、ですから当然これも「君が代」と同じく、天皇の長寿(皇室の永続)を祈念する意味作用を持っている。とするならば、「太宰」はその意味作用を読者のなかに喚起しながら、天皇の意志を体現した教育が「奥州の津々浦々にまで浸透」したことを言祝(ことほ)いでいたわけです。